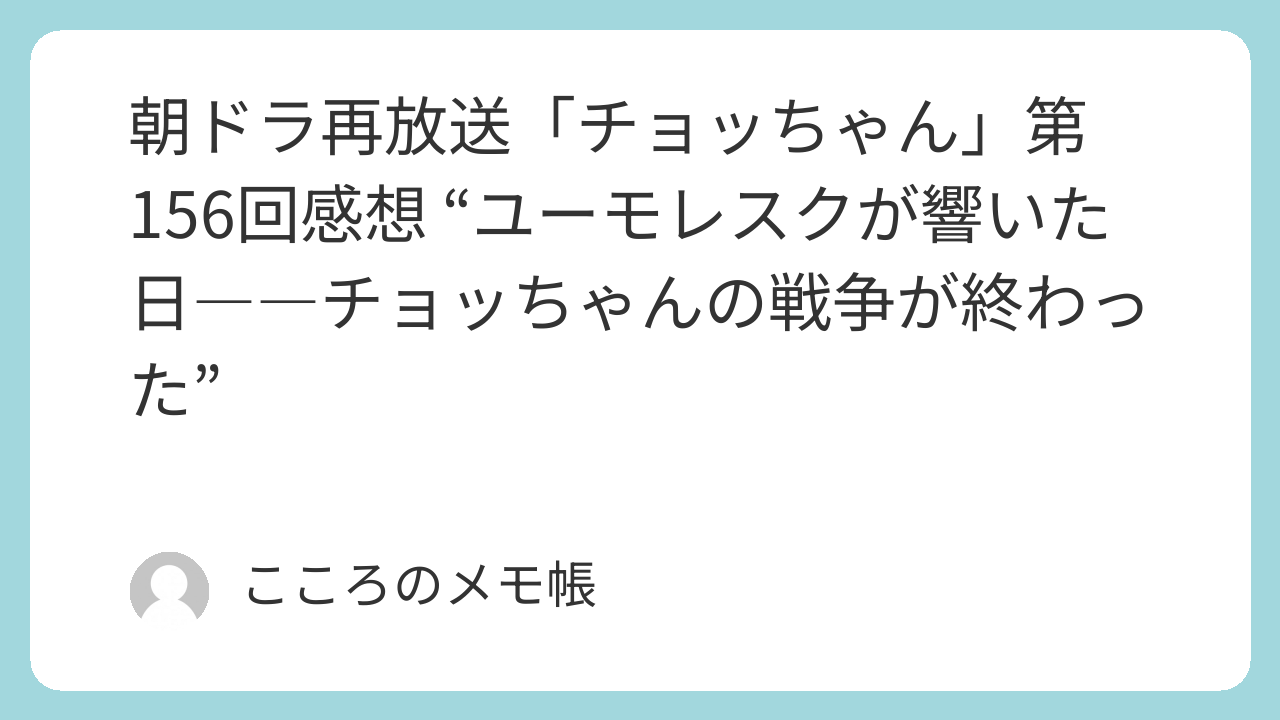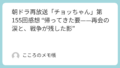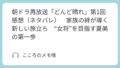本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
2025年10月11日放送 第156回
ざっくりあらすじ
- バイオリンを拒む要。坂上(笹野高史)が訪ねてきて、要(世良公則)を東都交響楽団のコンサートマスターに迎えたいと申し出る。しかし要は「怖いんだ」と首を横に振る。戦場で悲惨な光景を見続け、2年もバイオリンを弾かなかった自分に、もう“美しい音”を出せる自信がないというのだ。
- チョッちゃんの言葉。チョッちゃん(古村比呂)は、そんな要に「青森で出会った復員兵」の話をする。その兵士は、慰安会で聴いた「ユーモレスク」を今も口ずさんでいた。その旋律を弾いたのは、ほかでもない要だったのだ。チョッちゃんの「要さんの音は濁ってなんかいないわ」という言葉に背を押され、要はついにバイオリンを手に取る。
- 響き渡る「ユーモレスク」。最初はおぼつかない音色。けれど、やがて滑らかに広がる旋律に、家族や近所の人たちは笑みを浮かべながら聴き入る。この瞬間、岩崎家にとっての“戦争が終わった”のかもしれない。
- 邦ちゃんの再出発。時は流れ、要はコンサートマスターとして復帰。邦ちゃん(宮崎萬純)は再び女優の道へ戻る決意を語る。「へこたれないわよ。ちゃんと一人で生きていく。」戦争で失ったものを抱えながらも、再び前を向く邦ちゃんの姿に、時代の風が変わったことを感じる。
- 音吉の“試し”。中山家の金づちの音に文句を言いに行った要。実は音吉(片岡鶴太郎)がわざと叩いて“昔どおりかどうか”を確かめていた。「試したんですよ。文句言いに来るかどうか。そしたら来たじゃねえか。昔どおりでえ!」笑い合う要と音吉。平和な日常が戻ってきたことを実感する場面だった。
- 北海道・滝川にて。チョッちゃん一家は、俊道(佐藤慶)のお墓参りのため滝川を訪れる。「お母さんはね、小さい時から花摘みの名人だったんだから」「花の在りかを知ってるんだから」花を摘みながら笑うチョッちゃんの姿に、かつての少女のような明るさが戻っていた。そしてナレーションが呼びかける――「チョッちゃ~ん!」笑顔のまま、花を抱えて駆け出すチョッちゃん。半年間の物語がここで幕を閉じた。
今日のグッと来たセリフ&場面
| # | セリフ/場面 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | 要「怖いんだ。もし音が濁っていたら……」 | 戦争が残した“心の傷”を静かに語る、要の本音。 |
| 2 | チョッちゃん「要さんの音は、濁ってなんかいないわ!」 | 夫への愛と信頼、そして音楽への祈りのような言葉。 |
| 3 | 要が弾く「ユーモレスク」 | 岩崎家にとっての“戦争の終わり”。涙なしでは見られない。 |
| 4 | 邦ちゃん「へこたれないわよ、私。ちゃんと一人で生きていく。」 | 生涯の友として、チョッちゃんに続くように前を向く邦ちゃん。 |
| 5 | 音吉「試したんですよ。文句言いに来るかどうか。昔どおりでえ!」 | 音吉の粋な心遣い。平和が戻った証の笑顔。 |
| 6 | チョッちゃん「花の在りかを知ってるんだから」 | 物語の締めくくりにふさわしい象徴的なセリフ。生命の希望そのもの。 |
私が感じたポイント
-
「怖いんだ」――音を失ったバイオリニストの告白。坂上の誘いを前にしても、要の表情は晴れなかった。「俺は、ダメだよ」「バイオリンが弾けないんだよ」――その一言には、戦場で心を削られた男の苦しみがすべて詰まっていた。要は腕を負傷したわけではない。彼が失ったのは“音を信じる心”そのものだった。
「音が濁っていたらどうしよう」「あの頃の音がもう出せないかもしれない」――
それは演奏家としての不安を超えて、“人としての純粋さ”を失ったのではないかという恐れでもあった。戦前、息子の雅紀(相原千興)に「一日休めば三日遅れる」と教え、
自らにも厳しく課してきた要。その彼が二年も弾けなかった現実を前にすれば、自分を赦せなくなるのも当然だ。それでも坂上は、「お前のことだからすぐ取り戻せる」と笑ってくれた。かつて共に音楽を信じた仲間が、今も信じ続けてくれている。この場面は、“音を取り戻す前の静けさ”であり、要が再びバイオリンを手にするための“最後の沈黙”でもあった。 -
「ユーモレスク」が響いた日――チョッちゃんが信じた音、要が取り戻した心。加津子(藤重麻奈美)と音吉の軽妙なやり取り――「じゃ、小づちガンガン叩いても平気だね」と笑う音吉。そのユーモラスな日常の中に、要が抱える“音への恐怖”の重さが静かに描かれている。戦争は、音楽家・要の指だけでなく、心までも縛りつけてしまっていた。チョッちゃんはそんな要に、静かに語りかける。
「やめてもいいのよ」「でも、一度も弾かないまま決めるのは違うわ」
そして彼女が語る青森での復員兵の話――疎開先の妻がいなくなり、途方に暮れた男が、それでも「ユーモレスク」を口ずさんでいたという。その旋律を弾いたのが要であったと知った瞬間、要の強張っていた顔が少しずつほぐれ、「俺だよ」と微笑んで頷く。「要さんの音は、すさんでなんかいないわ。濁ってなんかいないわ。」チョッちゃんの言葉は、妻としてだけでなく、“音楽という希望”を信じるすべての人の代弁のようだった。ついに要はバイオリンを手にする。最初の音は震えていた。しかし、次第に音が空気を満たし、「ユーモレスク」が滑らかに流れはじめる。その旋律は、戦争が奪った“時間”と“心”を取り戻すかのようだった。みさ(由紀さおり)と俊継(服部賢悟)が玄関で立ち止まり、
加津子と音吉、はる(曽川留三子)が外からその音に耳を澄ませる。
家中に、そして通りにまで広がっていく“再生の音”。――この瞬間、岩崎家にとっての戦争は本当に終わったのだろう。
チョッちゃんの涙は、悲しみではなく、“生きる音が戻った”ことへの祈りのように見えた。
そして、視聴者の胸にも確かに残ったのは、「ユーモレスク」という曲名ではなく、
“信じる力が音を蘇らせる”という、この物語の根幹そのものだったのではないだろうか。 -
「そよ風の吹く町」――邦ちゃんが見つけた新しい空。時は流れ、要のバイオリンが「ハンガリー舞曲第5番」を奏でていた。その音を隣の部屋で聴きながら、チョッちゃんと邦ちゃんが並んで座っている。かつて共に戦火を生き抜いた二人が、ようやく“穏やかな日”を迎えていた。「要さん、もう大丈夫?」と邦ちゃんが尋ねる。「うん、もうあの通り。コンサートマスターになって張り切ってるの」と微笑むチョッちゃん。かつて夫の戦死に泣き崩れた邦ちゃんが、今は友の幸せをまっすぐに喜んでいる。そして、邦ちゃんの口から思いがけない言葉がこぼれる。「私、もう大丈夫だから。前の“大東キネマ”の人に、また女優にって誘われたのよ。」映画の題名は「そよ風の吹く町」。戦争の時代には決して生まれなかったような、“爽やかさ”と“希望”に満ちたタイトルだった。
「へこたれないわよ、私。もう、ちゃんと一人で生きていく。」
邦ちゃんのその言葉には、失った悲しみも、立ち直る強さも、すべてが詰まっている。彼女はもう、誰かに支えられる存在ではなく、自らの足で前を向く一人の女性になったのだ。戦争で傷ついた人々の中にも、新しい風は確かに吹き始めている。“そよ風の吹く町”という映画のタイトルが、邦ちゃん自身の今後の人生を象徴しているように思えた。 -
「昔どおりでえ!」――音が戻り、人が戻る瞬間。金づちの音が、軽やかに響く。
要のバイオリンの弓が止まり、「うるさいんだけどね」とため息をつく。その一言に、チョッちゃんと邦ちゃんは顔を見合わせて苦笑する。
――まるで戦前のようだ。「やめるように言ってきてくれないか」
要の口から出たその台詞は、かつてとまったく同じ。そしてチョッちゃんの返事も、「中山さんも、仕事なのよ」。あの頃の何気ない日常が、少しずつ戻ってきている。ついにしびれを切らした要が立ち上がり、「いい!俺が行く!」と勢いよく戸を叩く。「ちょっと!うるさいですよ!」と顔を出す要に、木づちを握った音吉が涼しい顔で言う――
「分かってますよ。」「なんだって!?」と食ってかかる要。だが音吉は笑って返す。
「試したんですよ。文句、言いにくるかどうか。
そしたら、来たじゃねえか。――昔どおりでえ!」その瞬間、要も、チョッちゃんも、はるも、みんなが笑い合った。
あの頃の「音の戦争」は、いまや“生きている証”に変わっていた。音吉は最後まで粋だった。本気の衝突ではなく、“昔どおりに怒れる”関係であることを確かめるために、あえて騒音を立てたのだ。音でつながり、音でぶつかり、それでも笑って「また明日」と言い合える――。このシーンは、戦後を生き抜いた人々がようやく取り戻した、
“音のある日常”そのものだった。 -
「花の在りかを知っている」――チョッちゃんの、最後の微笑み。季節は巡り、チョッちゃん一家は北海道・滝川へとやって来た。目的は、父・俊道のお墓参り。
馬車に揺られながら進む家族の姿。
――もし頼介が生きていれば、この馬車を引いていたのは彼だったのかもしれない。俊道のお墓に「ミルクキャラメル」をお供えする加津子と俊継。
要が言う。「お義父さん、今頃、道郎さんや頼介君と積もる話でもしてるんじゃないかな?」それにチョッちゃんが、「どんな話、してるんだろうね?」と穏やかに返す。「なんも、お父さんのことだ、相変わらずブスッとしてるんでない?」とみさが笑う。――その何気ないやり取りが、これまで失われた命の数々を優しく包み込むようだった。丘に咲く花々を摘むチョッちゃん、加津子、俊継。サイロの立つ風景の中で、チョッちゃんはまるで少女のように駆け回り、両手いっぱいに花を抱えている。
「お母さんはね、小さい時から花摘みの名人だったんだから!」と子どもたちに胸を張り、「花の在りかを知ってるんだから」と笑う。――“花の在りかを知っている”。
それは、どんな苦難の中でも希望を見つけられる力の象徴のようだった。チョッちゃんは、悲しみの中にも花を見つけ、絶望の中にも生きる喜びを見つけてきた。だからこそ、彼女はこの言葉を最後に残したのだろう。ナレーションが静かに呼びかける――「チョッちゃん。」振り向くチョッちゃん。「何?」
要とみさが顔を見合わせて、「え?」「なんも」と答える。そしてもう一度、今度は少し大きな声で呼びかけが響く――「チョッちゃ〜ん!」丘の上で花を抱え、満面の笑顔を見せるチョッちゃん。
その姿は、戦争を越え、時代を越えてもなお、“生きる”ということの眩しさを映していた。半年間の物語はここで幕を下ろす。けれどその笑顔と「花の在りかを知っている」という言葉は、これからもずっと、私たちの心のどこかで咲き続けていくだろう。
まとめ
第156回(最終回)は、“戦争を越えて生きる”という物語の真の終幕だった。要が音を取り戻し、邦ちゃんが夢を取り戻し、音吉が笑いを取り戻した。そしてチョッちゃんは、どんな苦難の中でも花を見つける力――
「花の在りかを知ってる」ことを、私たちに教えてくれた。
半年間の放送を通して描かれたのは、ただの戦後復興の物語ではない。
“生きることそのものの美しさ”だった。
「チョッちゃん」、本当におつかれさま。
そして、ありがとう。
『チョッちゃん』感想まとめはこちら
懐かしい朝ドラをもう一度見たい方はこちら → NHKオンデマンドでは見られないけどTSUTAYA DISCASで楽しめる朝ドラ5選