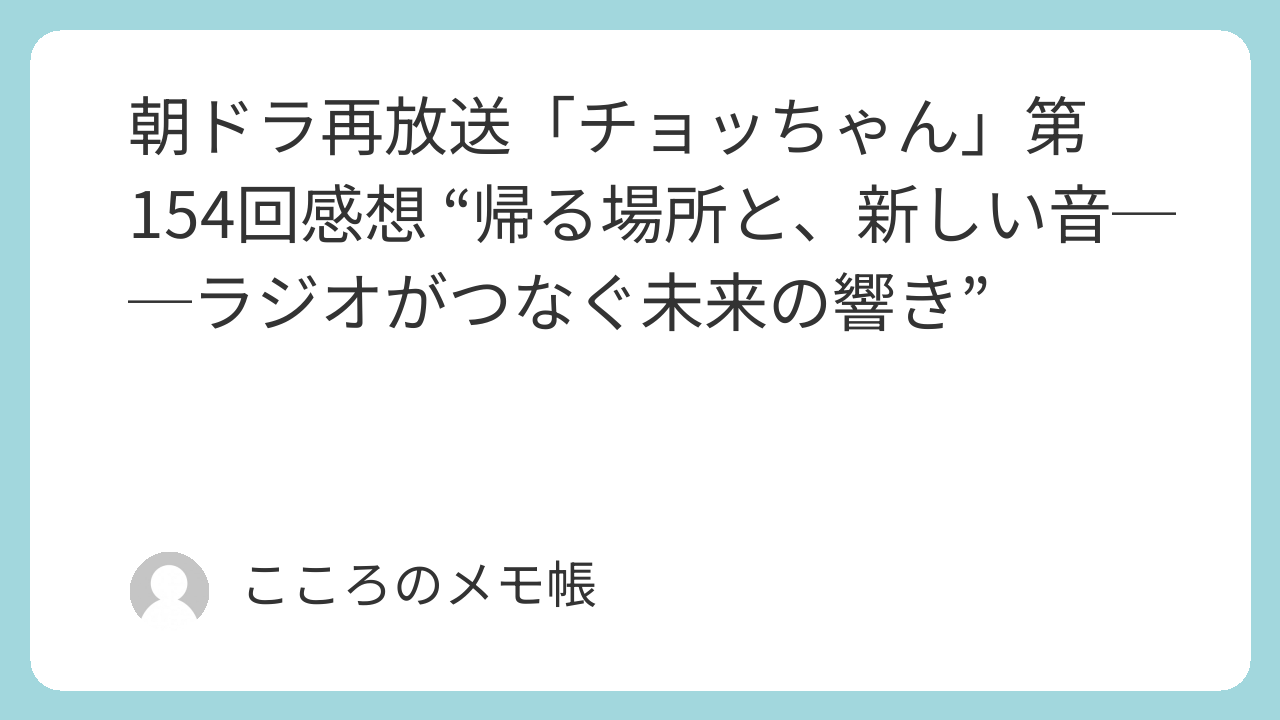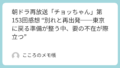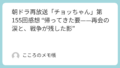本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
2025年10月9日放送 第154回
ざっくりあらすじ
-
諏訪ノ平での別れ。チョッちゃん(古村比呂)、みさ(由紀さおり)、加津子(藤重麻奈美)、俊継(服部賢悟)は、長く世話になった喜作(伊奈かっぺい)とよし(高柳葉子)に別れを告げる。戦後の厳しい暮らしを支えてくれた2人への感謝を述べ、涙の別れを交わす。良平(中野慎)は照れながらも「さいなら」とつぶやき、淡い別れの切なさが残る。
-
洗足への帰還。東京・洗足に着くと、音吉(片岡鶴太郎)とはる(曽川留三子)が出迎える。音吉たちが建ててくれた家は小屋どころか立派な建物で、一同感激。戦火を越えて再び帰ってこられたことへの喜びに包まれる。
-
再会と宴。夜には、泰輔(前田吟)、富子(佐藤オリエ)、連平(春風亭小朝)、たま(もたいまさこ)、夢助(金原亭小駒)、音吉夫妻、みんなが揃って帰京祝いの宴が開かれる。連平とたまの結婚をみんなが祝福。連平からチョッちゃんへのプレゼントは、なんと“ラジオ”。戦後の象徴のような贈り物に一同は歓喜する。
-
ラジオから流れる音楽。連平がラジオをつけると、流れてきたのはアメリカの曲「イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム(It’s Been a Long, Long Time)」。チョッちゃんは「こういう曲も聞けるようになったのね」としみじみ。戦争の終わりと共に訪れた“新しい時代の音”が、静かに家族を包み込む。
-
それぞれの新しい道。泰輔は「食堂をやる」と宣言。富子も賛同し、戦後の商売の再出発を決意する。チョッちゃんは青森と東京を行き来して、行商を続ける日々。連平とたまは雑貨屋を開こうと準備を進め、夢助は師匠のもとへ戻る。皆が新しい生活に踏み出す中、チョッちゃんは変わらず要の帰りを待ち続けていた。
-
邦子(宮崎萬純)との再会。ある日、チョッちゃんが洗濯をしていると邦子が訪ねてくる。お互いの無事を喜び合い、要や邦子の夫・大川(丹波義隆)の復員を祈る。そして、神谷先生(役所広司)からの手紙を読む。札幌で本屋を開く決意を記したその手紙には、教え子たちへの“卒業証書”のような言葉が綴られていた。
今日のグッと来たセリフ&場面
| # | セリフ/場面 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | チョッちゃん「中本さんのおかげで生きてこれたみたいなもんです」 | 青森での一年が、彼女の強さを育てたことを感じる別れの言葉。 |
| 2 | 良平の小さな「さいなら」 | 子どもの純粋な気持ちと別れの切なさが胸を打つ。 |
| 3 | チョッちゃん「音吉さん、本当にありがとうございました」 | 戦後の焼け跡に“家”を建てる音吉の力強さと優しさが沁みる。 |
| 4 | チョッちゃん「こういう曲も、聞けるようになったのね」 | ラジオから流れる洋楽に時代の変化と希望を感じる名場面。 |
| 5 | 泰輔「食べるものほど強いものはないね」 | 戦後を生き抜いた者の実感がこもるセリフ。生活の知恵と誇り。 |
| 6 | 神谷先生の手紙「君たちは、もう大丈夫だ」 | 教え子への最後の贈り物。涙なしでは読めない“卒業の言葉”。 |
用語メモ:「イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム(It’s Been a Long, Long Time)」とは
第二次世界大戦の終結直後、1945年にアメリカで発表されたポピュラーソング。作曲はジュール・スタイン、作詞はサミー・カーン。復員兵が長い年月を経て恋人と再会する喜びを歌った作品で、戦争から平和への移り変わりを象徴する楽曲。キティ・カレンやビング・クロスビーの歌唱で大ヒットした。劇中では、戦後の新しい時代の訪れと、再会を待つ人々の思いを重ねるように流れる。
私が感じたポイント
- 戦後を生き抜いた者同士の、静かな握手。「荷物は送ったのか?」という喜作の問いに、「手に持てるほどしかない」と答えるチョッちゃん。そして、「何もかんも、食べるものにかえてしまったんだべ?」と優しく言うよし。この短いやりとりの中に、戦後という時代の全てが凝縮されていたように思う。 飢えと寒さの中で、命をつなぐためにすべてを差し出してきた人たち。それでもなお、人を思いやる言葉をかけられる強さと優しさ。「季節になったらリンゴ送ってやるすけ」という喜作の一言には、疎開のきっかけを思い出させると同時に、“生きて再会できたこと”への感謝が滲んでいた。 彼らはただの疎開先の人ではない。チョッちゃんにとっての“もう一つの家族”だった。
- 「さいなら」に込めた小さな勇気。おそらく、良平にとっては加津子が初恋の相手だったのではないだろうか。子ども特有の照れくささから、素直に「さよなら」と言えない良平の姿が、なんとも愛おしい。そして俊継にとっても、兄・雅紀を失って以来、初めて「お兄ちゃん」と呼べる存在が良平だったのではないかと思う。三人の小さな友情と別れのシーンには、戦争を越えてもなお続く“子どもたちの時間”の尊さが滲んでいた。
-
青森での別れが示す“戦後の終止符”。
喜作やよし、良平との別れは、疎開生活の終わりを意味すると同時に、戦後を生き抜いた人々の温かさを再確認させる場面だった。「御引立て有難度う御座居ました」の張り紙に込められた言葉の重みが、戦争の終焉と新しい始まりを象徴していた。 -
青森で得た“生きる力”——疎開がくれた成長の時間。北海道に疎開するはずが、思いがけず青森県・諏訪ノ平に腰を落ち着けて一年余り。その間にチョッちゃんたちは、数えきれないほどの出来事を経験してきた。けれど、どんな場所でも前を向き、どんな状況でも順応してしまうのがチョッちゃんのすごさだ。青森での疎開生活は、北海道ではきっと得られなかった“生きる知恵”と“人との絆”を教えてくれた。チョッちゃんはこの一年で、一回りも二回りも大きく成長したように思う。
-
音吉の職人魂——“帰る場所”を形にした男。チョッちゃんが新しい建物を見て、「出来たのね。音吉さん、はるさん、ありがとうございます」と感謝を伝える。音吉は照れくさそうに「野々村さんや連平さんと作ったんだよ」と言うが、実際には音吉の腕と情熱があってこそ、ここまで立派な家が完成したことを視聴者は皆感じているはず。焼け跡から再び“家”を築くということ――それは単なる建築ではなく、人が生き直すための“希望”そのものを形にした音吉の職人魂だった。
-
涙と笑顔の宴——“失われた命”と“新しい絆”が交差する夜。チョッちゃん、みさ、加津子、俊継、泰輔、富子、音吉、はる、連平、たま、夢助──戦火を生き抜いた仲間たちが、久しぶりにひとつの屋根の下に集まった。「一人、頼介君が戦死したのは悔しいけどさ、これだけ顔が揃うとうれしいよ」と泰輔がつぶやく。その言葉に静かに頷く一同。誰もが頼介の不在を胸に抱きながら、それでも“今、生きていること”を噛みしめていた。そしてもう一方で、連平とたまという新しい夫婦が誕生していた。富子が「人も増えたし」と目を細め、チョッちゃんが「改めて結婚おめでとう」と祝福する。たまが照れ、連平が気恥ずかしそうに笑う。御徒町のバラックで始まった二人の暮らしは、決して豊かではないけれど、「狭いながらも楽しい我が家」という言葉の通り、確かな温もりに包まれている。失われた命を悼みながらも、新しい絆が生まれていく。戦後の混乱の中にあっても、人生はこうして少しずつ前へと動き出していくのだ。
-
“音の贈り物”——連平とたまからのラジオに込められた想い。「これね、あたしとたまから、チョッちゃんの帰京祝。開けてみて」──そう言って連平が差し出した風呂敷の中から現れたのは、一台のラジオだった。「中古なんだけど、つてで安く買えたから気にしないで」と笑う連平。だが、かつて「お金だけは持ってる」と言っていたたまの言葉を思い出すと、もしかしたら、たまが自分の大切なお金を出したのではないか──そんな想像が自然と胸をよぎる。それでも、チョッちゃんが気兼ねなく受け取れるように、あくまで軽やかに贈り物を渡す連平の優しさ。「遠慮なく、どうもありがとう!」と笑顔で受け取るチョッちゃんの姿に、これまで積み重ねてきた“信頼と友情の深さ”がにじんでいた。最終週まで見てきた視聴者なら誰もがわかる。チョッちゃんは、こういうとき決して遠慮などしない。それは、もらうことが“甘え”ではなく、“愛の受け取り方”だと知っているからだ。
-
ラジオがもたらす新しい時代の音。 “イッツ・ビーン・ア・ロング・ロング・タイム”が流れる瞬間、画面の空気が一変した。戦争中には聞けなかった洋楽が、今は自由に流れている。その音は、まるで「平和の証」のようだった。誰もが無言で聴き入り、しみじみと時代の移り変わりを噛みしめていた。
-
“食べることは生きること”——泰輔の決意に込められた再生の力。「叔父さんね、食堂やることに決めたよ。」泰輔がそう宣言する。その声には迷いがなかった。「世の中で何が強いかって。食べるものほど強いものはないね。」疎開生活を経て、泰輔がたどり着いた答えは“食べること”だった。それは、ただの商売の話ではない。人が生きるために最も根源的な行為、そして戦争で荒れ果てた社会をもう一度立て直すための“希望の仕事”だった。「疎開してさ、いろいろと勉強になったよ。」かつては行き当たりばったりだった泰輔が、経験を糧に未来を語るようになったこと自体が、戦後復興の象徴のように思える。この一言に凝縮されているのは、どんな出来事も無駄ではなく、すべてが“生きる力”へとつながっていくという真理だ。
-
それぞれの再出発が描かれた群像劇。泰輔の食堂、連平とたまの雑貨屋、夢助の再挑戦、そしてチョッちゃんの行商——それぞれが自分の道を選び始めた。戦争によって奪われた時間を取り戻すように、人々が再び“働く喜び”を見つけていく姿が感動的だった。
-
神谷先生からの“精神の卒業証書”。チョッちゃんのもとに届いた一通の手紙。差出人は、かつて空知高等女学校で彼女を導いた恩師・神谷先生。手紙にはこう綴られていた。札幌に残り、本屋を開く準備をしていること。5月に長男・拓(ひらく)が生まれたこと。
そして——「教え子の君や邦子君をいつまでも見守るという役からは、ここいらで解放してもらうことにします。君たちはもう大丈夫だ。私は、もう少しの心配もありません。」それは、長い年月を経て、ついにチョッちゃんたちが“神谷先生の教え”を胸に自立したことを告げる
まるで“卒業証書”のような手紙だった。チョッちゃんと邦ちゃんは、顔を見合わせて微笑み、静かに頷く。先生の言葉に込められた愛と信頼を、噛みしめるように受け止めながら。視聴者の多くがきっと思っただろう——心のどこかで、これからも迷ったときには、あの穏やかな声で導いてくれる“神谷先生”でいてほしいと。
まとめ
第154回は、“帰還”から“再生”へと向かう節目の回だった。
青森での別れ、東京での再会、そしてラジオの音——それぞれが戦後日本の希望を象徴している。焼け跡に建てられた家、ラジオから流れる音楽、人々の笑い声。
それらはすべて、チョッちゃんが失ったものを取り戻すための“小さな奇跡”だった。神谷先生の手紙が示した「君たちは、もう大丈夫だ」という言葉の通り、チョッちゃんたちはもう誰かに守られる存在ではなく、自分たちの力で未来を切り開く段階に入っている。
そして、要の帰還を信じて待ち続けるチョッちゃんの瞳には、
“戦後”を越えて“未来”を見据える力強さが宿っていた。
『チョッちゃん』感想まとめはこちら
懐かしい朝ドラをもう一度見たい方はこちら → NHKオンデマンドでは見られないけどTSUTAYA DISCASで楽しめる朝ドラ5選