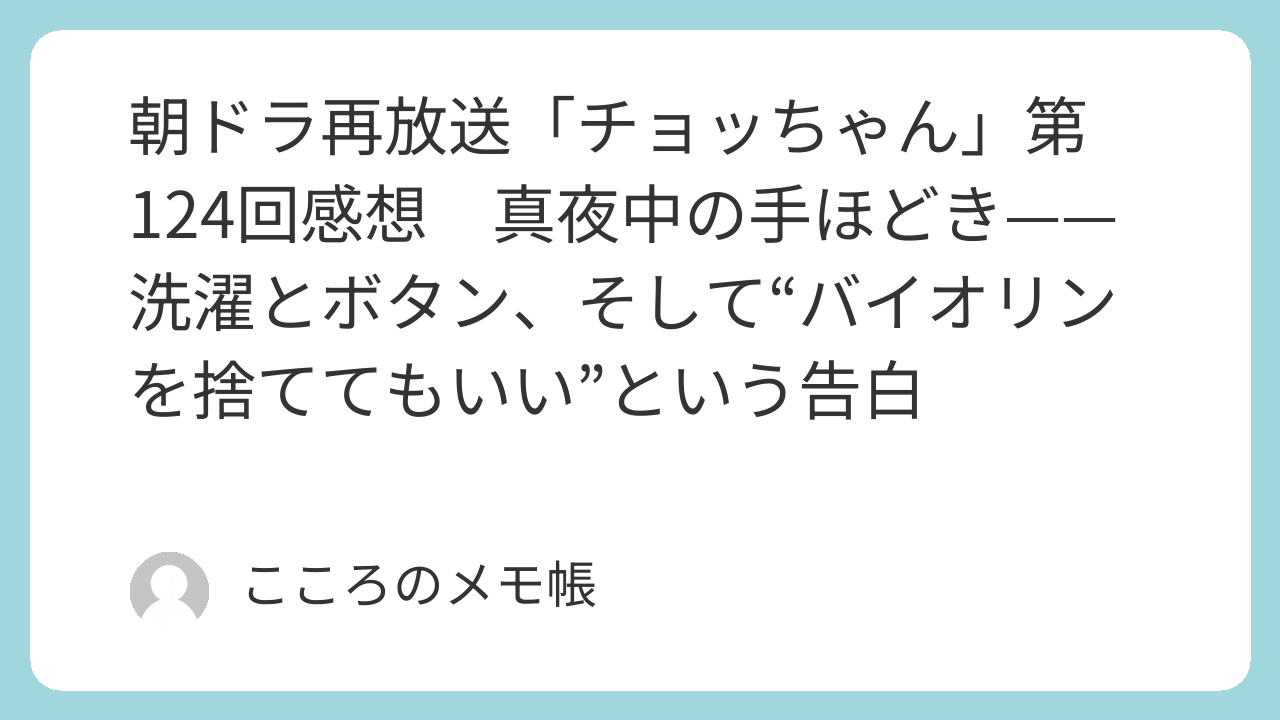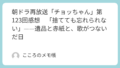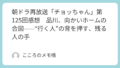本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
2025年9月4日放送 第124回
ざっくりあらすじ
-
入営前夜。 送別の客を見送ったあと、縁側で虫の音を聴く要(世良公則)と蝶子(古村比呂)。蝶子は、雅紀が逝った夕べも同じ音が鳴っていたと打ち明ける。「虫のオーケストラ」という雅紀の言葉が、静かな夜にふっと浮かぶ。
-
真夜中の“生活レッスン”。 時計が11時50分を回ったころ、蝶子は要に洗濯板の使い方を一から教え、続いて裁縫へ。糸の先を湿らせて絞り、ボタン付けの要領まで丁寧に伝える。「戦地で必要になるかもしれないから」。
-
針を動かす要を見つめて、蝶子がこぼす。「知らない土地で、こんなことを一人でやるのかと思ったら、かわいそう…」。要は「かわいそうなんて言うな。戦場へ行くんだ、覚悟だけは」と返すが、蝶子は「嫌! 絶対しない!」と拒む。
-
夫の本音。 結婚14年、初対面から16年。要はぽつりと核心を置く。「もし今、お前たちと一緒にいられる代わりに、バイオリンをやめろと言われたら——やめる。喜んで捨てるよ。」
-
聴かせておきたい音。 要は蝶子に頼み、眠る加津子(藤重麻奈美)と俊継(服部賢悟)を起こす。「今日のうちに、俺のバイオリンを聴かせておきたい」。そして真夜中の居間に「ユーモレスク」が満ちる。泣き腫らした目で、蝶子はその音を刻むように聴く——“聴き納め”になるかもしれない音として。
今日のグッと来たセリフ&場面
| # | セリフ/場面 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | 要「明日は晴れそうだね」 | 何でもない天気の挨拶が、別れの前夜には胸に刺さる。 |
| 2 | 蝶子「虫のオーケストラって、マーちゃんが…」 | 喪の記憶と今夜が一本でつながるモチーフ。 |
| 3 | たらい・洗濯板・石けんの“実地訓練” | 家事の所作が、そのまま生き延びる術になる。 |
| 4 | 蝶子「かわいそう…」→要「言うな」 | “覚悟”と“生きて帰ってほしい”の真っ向衝突。 |
| 5 | 要「あんな帽子は形が好かん。ゲートルなんてしたこともない」 | 軍装が似合わない男の、ささやかな抵抗。 |
| 6 | 要「今、お前たちと一緒にいられるなら、バイオリンを捨てる」 | “音楽の人”が家族を選ぶと宣言した夜。 |
| 7 | 蝶子「絶対、死んじゃダメ」 | “覚悟”を拒否する、生活者の強い否。 |
| 8 | 要「子どもたちを起こしてくれんかね」 | 明日の不在に備える、父の最後の授業。 |
| 9 | 真夜中の「ユーモレスク」 | 家族に刻んだ“音の遺影”——でも遺影にしたくない音。 |
私が感じたポイント
-
家事の手ほどき=愛の手ほどき。 洗濯やボタン付けの細部を映し続ける演出が、とにかく贅沢。糸を舐めて撚り、針穴を探るその数十秒が、二人の14年の積み重ねを可視化した。
-
“覚悟を拒む”という愛のかたち。 要は覚悟を求め、蝶子は「嫌」と真顔で跳ね返す。戦場の論理より生活の論理を前に置く——それがこのドラマの芯だと思う。
-
柱時計の振り子が、16年前の始まりからいまへ――コツ、コツと針を進めるたびに、要の言葉が研ぎ澄まされていく。「死ぬことは大して怖くない。けれど、さみしいと思うんだ」。覚悟の強がりじゃない。残される側の顔がはっきり見えてしまう男の本音だ。そして核心。「もし、いまお前たちと一緒にいられる代わりにバイオリンをやめろと言われたら、俺はやめる。喜んで捨てる」。16年前、何よりも“腕”を守り、生活のための演奏はしないと言い切った男が、いまは“家族”を守るためにバイオリンを手放してもいいと言う。雅紀の死を越え、14年の生活が積み上げたものは、技ではなく優先順位の更新だった。要は天才である前に父になり、演奏家である前に夫になった。その穏やかな表情は、敗北ではなく選択の誇りだ。
-
“虫のオーケストラ”が鳴らす生と死。 あの夕べも今夜も鳴る虫の音。同じ音の上で、別の物語が進む残酷さと美しさ。この反復が、戦時の日常を静かに刻む。
用語メモ(さっとおさらい)
-
ゲートル:布やフェルトの脚巻き。ふくらはぎから足首に巻き付け、ズボンの裾を固定したり、泥・小石の侵入や脚の疲れを防ぐために兵隊が用いた装備。日本軍では行軍の実用品だった。
まとめ——“聴き納め”にしないための約束
要は音で「さよなら」を言いにいくのではなく、帰ってくる場所の音を家族に残した。蝶子は「覚悟なんかしない」と生の側に立ち続けた。
真夜中の「ユーモレスク」が、どうか“最後”の印ではなく“つづき”の前奏でありますように。
あなたなら——別れの前夜、何を手ほどきし、どんな音を残しますか?
『チョッちゃん』感想まとめはこちら
懐かしい朝ドラをもう一度見たい方はこちら → NHKオンデマンドでは見られないけどTSUTAYA DISCASで楽しめる朝ドラ5選