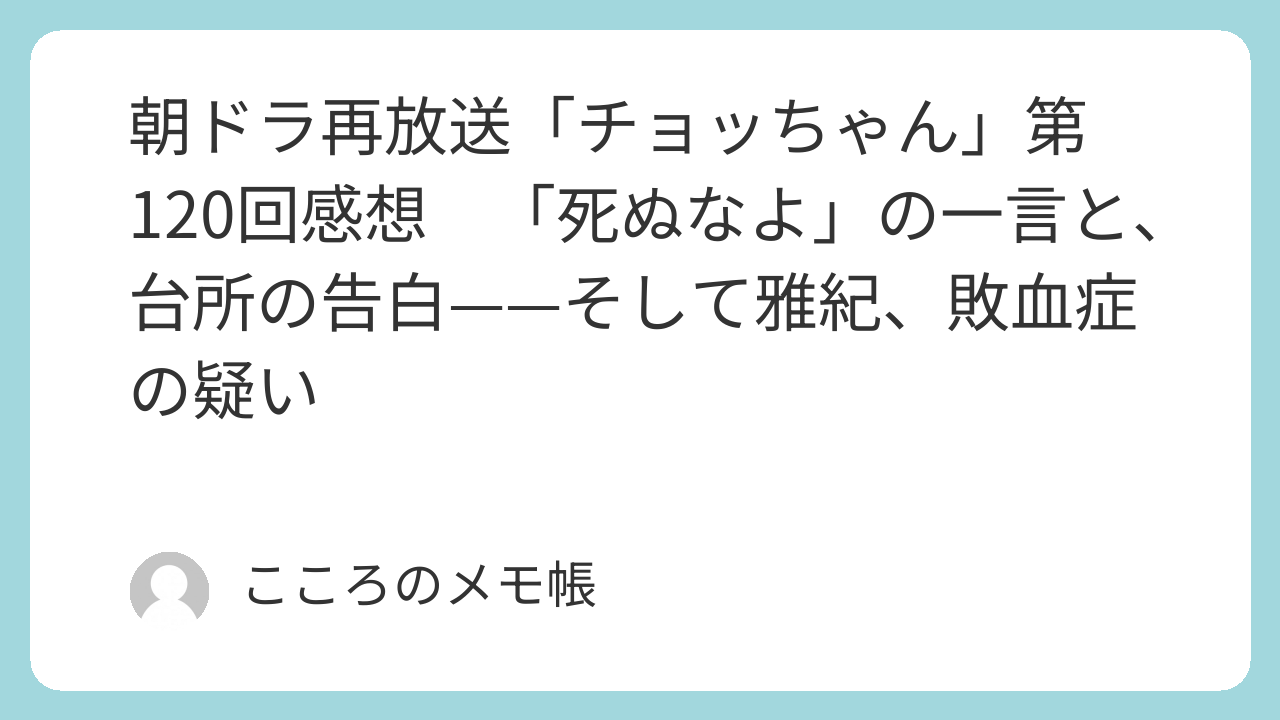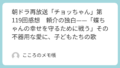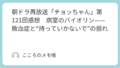本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
2025年8月30日放送 第120回
ざっくりあらすじ
-
出征前の頼介(杉本哲太)が洗足の岩崎家を辞した直後、要(世良公則)が帰宅。頼介は敬礼で応え、要は「非常時こそ、笑いや音楽が要る」と告げる。頼介は無言の微笑みで受け止め、要の「死ぬなよ」に背を向けて歩き出す。
-
台所。要は「頼介君は、ずっと君(蝶子)を思っていたね」と切り出し、蝶子(古村比呂)は東京に発つ前日にその気持ちに気づいていたと明かす。過去の不器用さを悔やみ、邦子(宮崎萬純)に言われた「気づかないのは一種の罪」を思い出して泣き崩れ、要が抱きとめる。
-
日を置いて——蝶子は滝川の父母へ手紙。俊道(佐藤慶)が2~3日寝込んだ件、洞爺湖近くに昭和新山が生まれた新聞記事の不気味さ、夢助(金原亭小駒)と大川(丹波義隆)の応召、そして頼介が出征挨拶に来たことを綴る。
-
子どもたちが表でけんけん遊び。音吉(片岡鶴太郎)も混じる中、雅紀(相原千興)が突然倒れる。熱と悪寒。翌朝の往診医(宮沢元)は「風邪」と診立てるが、3~4日経っても回復せず、大病院へ。
-
黒木医師(大門正明)は詳しく問診のうえ、「敗血症の疑い」として直ちに入院を指示。看護婦・横山里子(吉田やすこ)が手続きを進める。ナレーションは「不吉な予感が当たってしまいました」で幕。
今日のグッと来たセリフ&場面
| # | セリフ/場面 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | 要→頼介「こういう非常時だからこそ、余計に笑いや音楽が要る」 | “芸の存在理由”を一行で言い切る。 |
| 2 | 頼介の無言の微笑 | 反論も敬礼も越えた、覚悟の交換。 |
| 3 | 要「頼介君は、ずっと君を思っていたね」 | 頼介の想いに“気づいていた”ことを夫に打ち明ける—夫婦で真実を共有。 |
| 4 | 蝶子「気づかないのは一種の罪だって…」 | 自責と赦しのあいだで涙が決壊。 |
| 5 | 手紙の一節:昭和新山の記事にざわつく心 | 画面外の“地の変動”が家庭の胸騒ぎへ。 |
| 6 | 音吉とけんけんぱ→雅紀が弾きながら倒れる | 「休むと戻るのに三倍」のロジックと身体の限界の衝突。 |
| 7 | 町医者「風邪でしょう」→黒木医師「敗血症の疑い」 | 安堵が反転する二段診断。 |
| 8 | 黒木医師→看護婦・横山「すぐ入院の手続きを」 | 迷いを切る現場の決断。 |
私が感じたポイント
-
非常時に“芸は不要か”問題、今日の決着。 要(世良公則)の一言は、戦時下の「役に立つ/立たない」論へ真正面からの応答。人の心を支えるものは、非常時ほど必要だと改めて腹に落ちた。
-
“気づけなかった”自分を抱きしめ直すシーン。 「気づかないのは一種の罪」を蝶子(古村比呂)が自分に向ける痛み。要の大きな腕と低い声が、その罪悪感を生活の温度へ戻してくれた。頼介(杉本哲太)への礼として歌を用意した前回の続きとしても胸に沁みる。
-
昭和新山という“地のうねり”。 洞爺湖の近くに新しい山が生まれた——新聞越しでも伝わる不穏。自然の変動と社会の戦時化が、同じ“胸騒ぎ”として蝶子の心に重なる描写が巧い。
-
父のロジック vs 子の身体。 「1日休むと戻るのに3日」の音楽家の算術を信じたい要と、「今日は異常だ」と感じ取る親の直感——その綱引きの末の倒れる音。教育の熱が、医療の判断にバトンを渡す瞬間でもあった。
-
音吉との空気の雪解け。 冒頭の挨拶は柔らかく、わだかまりは一旦脇へ。ご近所力が緊急時に機能するための“日常の挨拶”の大事さを思う。
-
(※個人的に——今はどうか分からないが、昭和新山は札幌の小学校時代の修学旅行の定番で、自分も6年生で訪れた場所。あの頃はピンと来なかったけれど、物語の時代に“生まれた山”だと知ると一気に意味が変わる。)
用語メモ(さっとおさらい)
-
応召(おうしょう):召集命令に応じて出頭すること。召集令状(俗に“赤紙”)が届いた後、指定日時・場所へ赴く行為を指す。入営(にゅうえい)は部隊に編入される段階をいう。
-
昭和新山(しょうわしんざん):北海道・洞爺湖の南、有珠山の麓に1943〜45年ごろ出現した溶岩ドーム。畑が隆起して“新しい山”が生まれた。戦時下の日本で、「地面そのものが変わる」出来事として大きな話題に。
まとめ——“生きて帰れ”の祈りと、病室の灯り
要の「死ぬなよ」は、頼介に向けた芸の人の祈りだった。だが次の瞬間、家の中では子の高熱という現実が始まる。非常時に必要なのは、言葉と音、そして素早い段取り。黒木医師と横山看護婦の判断に救われながら、ただただ雅紀の回復を願う一日になった。
明日、どの家の戸口を“赤紙”が叩くのかは分からない。だからこそ、笑いと音楽を絶やさないこと、そして異変を見逃さないこと——この二つを両手で抱えて、次の一話へ。
『チョッちゃん』感想まとめはこちら
懐かしい朝ドラをもう一度見たい方はこちら → NHKオンデマンドでは見られないけどTSUTAYA DISCASで楽しめる朝ドラ5選