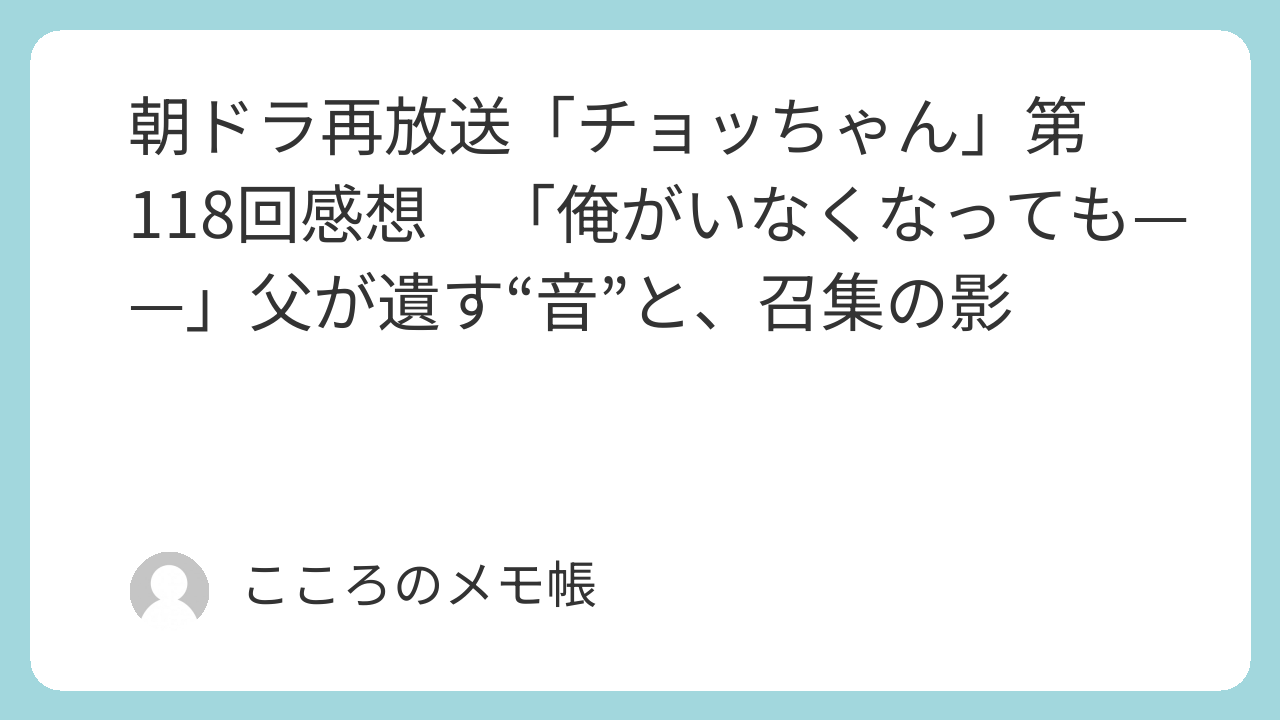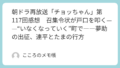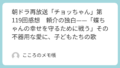本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
2025年8月28日放送 第118回
ざっくりあらすじ
-
出征者の見送りから戻った要(世良公則)は、坂上(笹野高史)と楽団員の減少を嘆く。先月結婚したばかりの松川(※団員)が召集、妻は人前では涙をこらえていたと語られる。
-
家では、雅紀(相原千興)のバイオリン稽古がさらに厳しさを増す。台所の蝶子(古村比呂)と加津子(藤重麻奈美)の耳にも、要の怒声が刺さる。
-
ついに蝶子が直談判。「どうしてそこまで?」——要は自分に残された時間を口にする。召集が来たら戦地へ行く、死ぬことだってある。その時、父として何を子どもに残せるのか——それは技術と耳と心だ、と。
-
会話を廊下で聞いていた雅紀は、涙を拭いて「僕、ちゃんとやる」と宣言。要も胸の内を見せて初めて、親子の稽古の温度が一段変わる。
-
音吉(片岡鶴太郎)とはる(曽川留三子)が家前で掃除。音色が変わったことに気づく。そこへ邦子(宮崎萬純)が来訪——夫・大川(丹波義隆)の入営を報告して一晩泊まることに。
-
さらに安乃(貝ますみ)から、兄・頼介(杉本哲太)が戦地に行くと告げられる。戦争は、岩崎家の周りから次々と“人”を奪っていく。
今日のグッと来たセリフ&場面
| # | セリフ/場面 | ワンポイント |
|---|---|---|
| 1 | 坂上「妻子ある男を戦地へ連れてっちゃいけないよ」 | 皮肉にも自分にも降りかかる現実認識。笑いでごまかす余白が消える。 |
| 2 | 要「俺にはね、時間がないんだ」 | 今日の核心ワード。以降の独白が滝のようにあふれる前触れ。 |
| 3 | 要「死んだ者のことは、時が経てば忘れる。だから“忘れようにも忘れられないもの”を残したい」 | “遺産=モノ”ではなく“技能・審美眼・感動する心”。価値の転換が胸に刺さる。 |
| 4 | 要「形は壊れる。壊れないのは、腕と耳と心だ」 | バイオリニストの遺言。教育観の核。 |
| 5 | 要「俺がいなくなっても……雅紀が弾けば、それは俺だ」 | 涙腺決壊ポイント。音は継承される“居場所”。 |
| 6 | 雅紀「僕、ちゃんとやるから。怒られても平気」 | 子どもが“叱責”を“継承”に置き換えた瞬間。 |
| 7 | 音吉「マーちゃん、俺のこと嫌ってるかな?」 | 大人のプライドの裏にある寂しさ。近所力の温度が滲む。 |
| 8 | 邦子「今日、入営したの」 | 口に出すだけで現実になる。静かな破裂音。 |
| 9 | 安乃「兄が、戦地に行くことになりました」 | 戦争が“隣の家”から“自分の家”になる一行。 |
要の“独白”をもう一度(抜き書き+要約)
俺には、時間がない。 召集が来たら、逃げ隠れはできない。戦場に行く。死ぬことだって、ある。
死んだ者は忘れられていく。 それが寂しい。だから、忘れようにも忘れられないものを子どもの中に残したい。
残すべきは形じゃない。形は壊れる。残るのは技術、いい音を弾ける腕、いい音を聴き分ける耳、そしていい音に感動できる心だ。
それさえ刻めれば、俺がいなくなっても、雅紀が弾けばそれは“俺の音”だ。君(蝶子)は、いつだって僕のバイオリンを聴ける。
(台詞の骨子をかみ砕き再掲。今日の名場面を保存しておきたい人向けの“抜き書き”。)
私が感じたポイント
-
“教育=遺言”という発想の反転。 収入も家も写真も、戦争が一瞬で奪うものだらけの時代。だからこそ要(世良公則)は、奪えないもの=身体化された知を遺すと決めた。職人の哲学が父の言葉になった瞬間だと思う。
-
厳しさの翻訳が起きた日。 これまで“鬼”にしか見えなかった稽古が、今日からは愛の遺言に変わる。要の独白を雅紀(相原千興)自身の言葉で受け止めた脚本・演出に拍手。
-
“泣けない”妻の話。 松川の妻は、人前では泣けない。非国民というラベルが涙にまで張り付く。坂上(笹野高史)の「今頃きっと泣いてる」に、見えない場所での悲しみの連鎖を思う。
-
音吉の小さな自尊心。 「嫌われたかな?」の一言に、遊びを奪われた側の寂しさがにじむ。はる(曽川留三子)の緩衝材力が、今日も家々の温度を保っていた。
-
“いなくなる”列が伸びる。 邦子(宮崎萬純)の大川(丹波義隆)、安乃(貝ますみ)の頼介(杉本哲太)。名を呼べる人が次々と遠くへ行く重さ。ドラマが個人名で戦争を描く強さに、改めて心をつかまれた。
用語メモ(さっとおさらい)
-
入営(にゅうえい):召集後、指定部隊へ入隊・編入すること。見送りの“万歳”は儀礼化された慣習でもあるが、家の中では涙の始まり。
-
召集(しょうしゅう):兵役義務者に出頭を命じること。俗に赤紙。拒否の余地はほぼ無い。
まとめ——“音”は戦場へ行かない
要が遺そうとしているのは、壊れないもの=音楽家としての身体だ。音は人の中に宿り、時間を越えて鳴り続ける。だからこそ、雅紀が弾けばそれは要——父の居場所は、子の音に残る。
一方で“いなくなる人”が増え続ける現実は止まらない。明日、どの家の戸口を赤紙が叩くのか。そんな時代に、私たちは何を遺して生きるのか。
あなたなら、誰かに“忘れようにも忘れられないもの”を遺すとしたら、何を選びますか?
『チョッちゃん』感想まとめはこちら
懐かしい朝ドラをもう一度見たい方はこちら → NHKオンデマンドでは見られないけどTSUTAYA DISCASで楽しめる朝ドラ5選